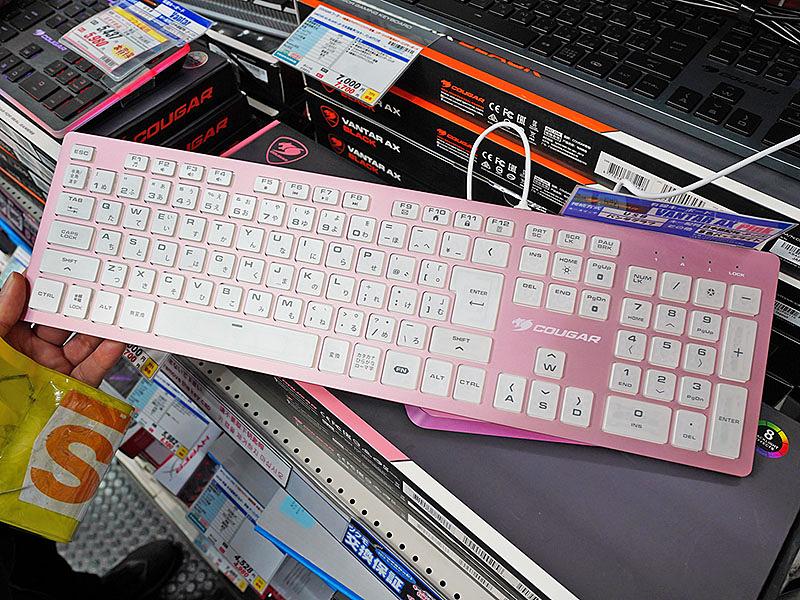オリビア・コールマン「“母親=完璧”。その必要はないと感じられた」 Netflix「ロスト・ドーター」を語る
演技派女優マギー・ギレンホールが初監督に挑戦したNetflix作品「ロスト・ドーター」が、ニューヨークのSVAシアターで特別上映された。上映後のQ&Aには、ギレンホール監督のほか、キャストのオリビア・コールマン、ダコタ・ジョンソン、ピーター・サースガードらが登壇し、製作秘話を明かしてくれた。(取材・文/細木信宏 Nobuhiro Hosoki)【フォトギャラリー】「ロスト・ドーター」会見の様子 本作は、イタリアの作家エレナ・フェッランテの小説を映画化した作品。ギリシャの海辺の町へバカンスにやって来た中年女性レイダ(コールマン)は、ビーチで見かけた若い母親ニーナ(ジョンソン)と幼い娘の姿に目を奪われる。母娘の関係に動揺したレイダは、かつて自分が母親になったばかりで恐怖と混乱に満ちていた頃の記憶に押しつぶされそうになり、心の中の不気味な世界へと迷い込んでいく。 「秘密」でスクリーンデビューを果たしたギレンホールは、「セクレタリー」で頭角を現し、「ダークナイト」「クレイジー・ハート」などで高い評価を受けてきた。まずはフェッランテの原作小説と出合うまでの過程を明かしてくれた。 ギレンホール「フェッランテの4部作『ナポリの物語』シリーズの『リラとわたし』、その後に出版されたばかりの『新しい名字』も読んで、かなりの衝撃を受けたんです。これまでも、音楽、本、映画を通して、女性の魅力的な表現を目にしたり、耳にしたりしてきましたが、自分に合っていると思えた作品はありませんでした。それらの作品に多くの時間を費やし、自分に適した作品を取り入れようとしてきましたが、結局、それらは何かが不足していたり、何かが過剰に思えたんです」 だが、フェッランテの紡いだ物語は、これまでの取り入れた作品群とは“何か”が違った。 ギレンホール監督「まず『この本に書かれている女性(=レイダ)は最悪だ!』と思いました。でも、それから10秒くらい経った後、彼女にとても共感を抱けると感じたんです。なぜかというと『私も最低の女性。この感覚は、多くの女性が経験するような共通の感覚だけど、誰にも共有されないことなの?』と考えたんです。原作を初めて読んだ時、世界中の人々と同様に、私もひとりきりでそんな感覚を持ちました。この映画館にいるような(私が)知らない人、あるいは母親、夫、娘と、この作品を共有することができれば良いと考え、映画化に挑戦してみたんです」 フェッランテは、処女作から“自身の匿名性”を条件にしている人物だ。本名を明かしておらず、本人のことを知る人は誰もいない。そのような人物に、どうやってアプローチし、映画化を進めることができたのだろう。 ギレンホール監督「この点に関しては色々言いたいことがありますが、簡潔に説明しますね。まず最初に、本の著作権を得るために(手紙のような)メールを書きました。もちろん、私も彼女がどんな人物か知りません。出版社を介して、メールのやりとりをしていたんです。実は、そのメールも数週間をかけて書いています。そこで『監督をしたいこと』『原作を脚色したいこと』『なぜそうしたいのか』を伝えました。彼女は『イエス』と応じてくれましたが『あなたが監督をしなければ、この契約は無効です』と言われました」 フェッランテは、ギレンホール監督をかなり気に入ったようだ。「The Guardian」に寄稿した記事では「もしも、マギーが男性だったら、(原作を)このように自由に手掛けさせてはいなかった」と語るほど信頼を寄せている。 コールマンが演じたレイダは、母であり、妻、恋人、そして教授である複雑な役どころ。コールマンは、ギレンホール監督とどのようにキャラクターを創り上げていったのだろうか。 コールマン「マギーとニューヨークでランチした時は、膝が震えるほど興奮しました。読ませてもらった脚本は、これまで演じたことがないような役柄だったからです。教授という導入の設定も、私には知識がなかったんですが、母親、妻、そして恋人の部分に関しても、これほど正直な役柄は巡り合ったことがなかった。実生活の私は、良い母親だと思っています。でも、母親として疲れている時もあれば、誇りに思えない瞬間もありました。でも、この役柄を通じて『母親として完璧である必要はない』と初めて感じることができたんです。ずっと素晴らしくなくても、苦手なことがあっても良い――演技をすることに興奮する役柄でした。だからこそ、この映画を見た女性の観客は、立ち上がって『イエス』と言いたくなると思います。世の中の女性は、誰もが『私は狂っている』と感じてしまう瞬間があります。『(女性として)自分は狂っている』と感じてしまう人は、実際にたくさんいるんです」 実生活ではギレンホール監督の夫でもあるサースガードは、若き日のレイダが惹かれるハーディ教授役として出演。「実は、演技で失敗したくなかったので、すごく神経質になっていたんです。なぜなら、自分の妻の前でそうなってしまったら、すごく恥ずかしいし、屈辱的なことだから。それに、ハーディ教授は全ての女性が一緒にいたいと思える“欲望の対象”になるような男性。これまでそんな役を演じたことはありませんでした。監督は『この役が適している』と思ってくれていたが、僕にはそう思えなかったんです」(サースガード)。そんな思いを抱えていると、ギレンホール監督はある要求をしてきたそうだ。 サースガード「『(劇中で)実際に授業をやっている姿を見せて欲しい』と。もちろん僕は学者ではないですし、学生時代もむしろ最悪な学生でした。でも、この(演技で)講義をすることのアイデアには、夢中になれたんです。そこで、監督の友人で、実際に教授をしているドミニク・タウンゼントさんの助けを借りました。僕が憧れる教授の講義をYouTubeで見たり、彼らが書いた著書なども読みました。でも、普段の生活でやっていないことですから、大勢の人々の前で話すことは、俳優としてかなり神経質になっていました」 ジョンソンは、ギレンホール監督について「さまざまな種類の映画を通して、でたらめや、いい加減な現場も体験してきている。だからこそ、何がピュアで、何が正直で、何が安全かを理解し、まっすぐに演出をしていた印象でした」と振り返る。 ジョンソン「今作では、仕事をしているという感覚がなかったんです。アート作品を手掛けているような感覚でした。自分の本心をアートで表現している感じ。それは他の俳優やスタッフも同じだったと思います。まるで家族のように、誰もが支え合っていました。ハードなシーンでも、誰もがその場にいてくれたんです。そのため、自分の部屋に戻った時に、この職業を選んだことについて泣いたり、後悔することもありませんでした。以前はそんなことが沢山あったんです。重要だったのは、マギー監督のもとでは、(人間的に)美しいシーンでも、醜いシーンでも、演じるうえで完全に安心できる。私にとっては完璧なことでした」 本作は、現在と過去、2つの時間軸を交差して描いており、TVシリーズ「チェルノブイリ」のジェシー・バックリーが若き日のレイダを演じている。コールマンは、同様の人物を演じることになったバックリーとのコミュニケーションについても言及した。 コールマン「全ては脚本に書かれていました。だから、ジェシーとは、脚本について一度語り合っただけです。私とジェシーは全く異なった人間ですが、お互いを理解し合うことができました。ある女性における20代、そして30代、40代は、同じ人物だったとしても全く異なるものになると思うんです。だから、我々もあえて違ったままで良いと考えましたし、マギー監督も『会う必要はない。物事を大きくしなくてもいい』と言ってくれました。脚本に記されていた道標が明確でしたから、大きく失敗するような演技をすることはありませんでした」 「ロスト・ドーター」は、Netflixで配信中。